読んでいる皆様、こんばんは。
本日は一旦冬の寒さにもどってしまいましたね。寒さに震えながらずっと仕事をしておりました投稿主の織‐シキ‐です。
今回は、「PokémonLEGENDSアルセウス」を先日一通りクリアしましたので感想とかを書いていこうと思います。少しでも購入の参考になれば嬉しいです。
それではどうぞ。
ゲーム概要
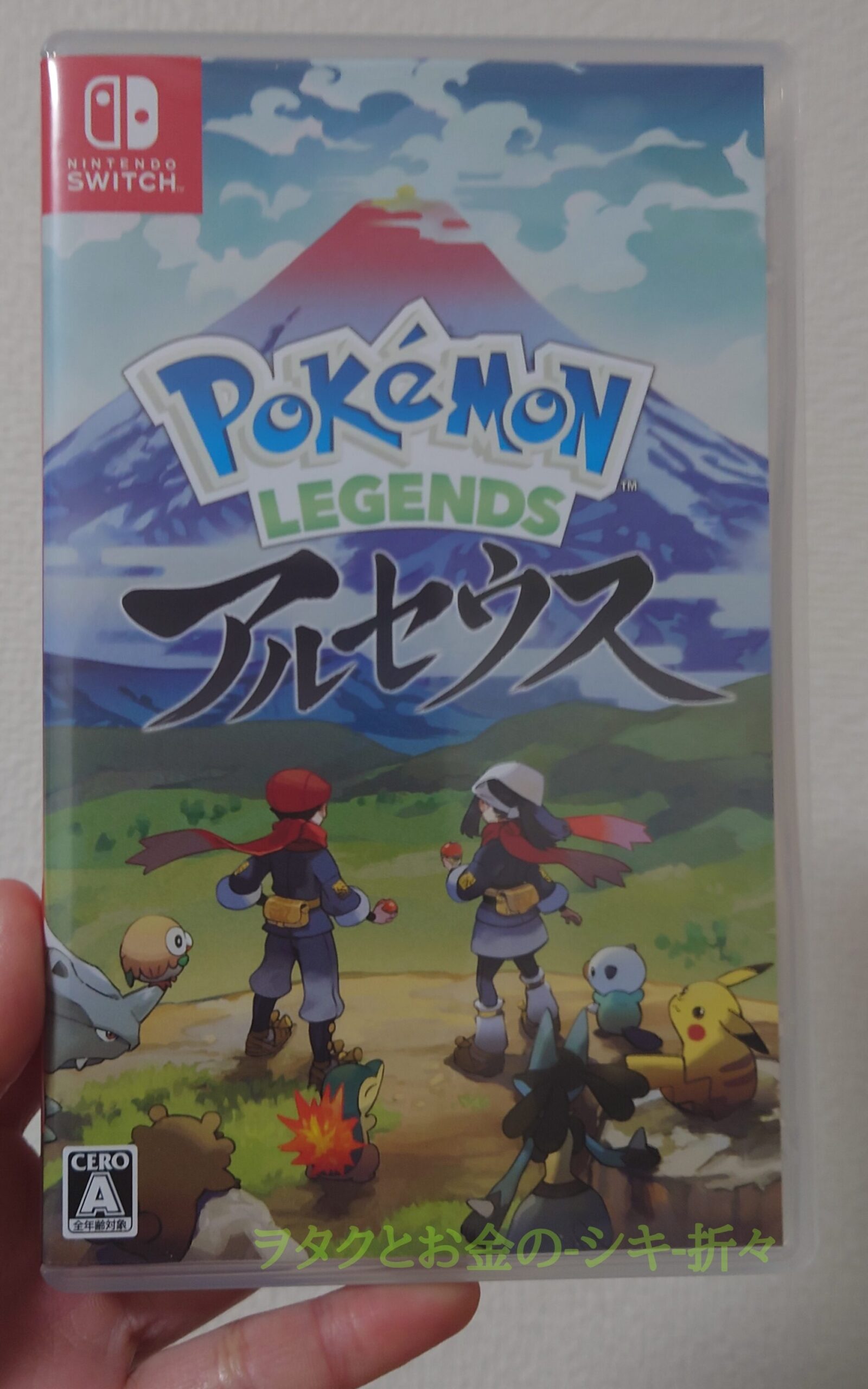
発売日:2022年1月28日(金)
発売:株式会社ポケモン
販売:任天堂株式会社
開発:株式会社ゲームフリーク
ジャンル:アクションRPG
機種:Switch専用
良かった点
主個人としては以下はよかったと思いました。
- ポケモン集めが楽しい
- フォトモードでお気に入りのポケモンとのツーショット
- 広くて懐かしい新しいヒスイ地方の冒険
それでは、一つ一つ解説していこうと思います。
ポケモン集めが楽しい
今回はとにかくポケモン集めが楽しいです。
図鑑のタスクを埋めるのももちろんですが、今までが
草むらorシンボルエンカウントで遭遇→バトル→ゲット
でしたが
フィールドのシンボルを見つける→ロックオン→そのままボールを投げる→ゲット
ということができます。
なのでバトルを挟まず直接ゲットできることにとても感動しました!
特に大量発生時や時空のゆがみが発生した際はたくさんポケモンが集まるので沢山ボールを投げて沢山無駄遣いしてしまいました。(笑)
もちろん気性が激しいポケモンだったりは見つかってしまい、バトルしないと捕まえられないのでそこは今まで通りのポケモンのゲットの仕方だとも感じられます。
図鑑集めは楽しいところもあるのですが、特定の場所でしかでないポケモンもいたり探すのはとても大変でした。ちなみに主が最後の最後まで見つからななかったのは「ピチュー」でした(笑)
進化についても従来の通信交換などで進化させることもできるのですが、2タイトル同時発売ではなくこの1作品だけなのでそのあたりも配慮されていました。
過去のスピンオフでも登場していた通信ケーブルに似たアイテムの「つながりのひも」だったり、「あやしいパッチ」や「プロテクター」などを持たせるではなく、「リーフのいし」や「かみなりのいし」のようにアイテムを使用してそのまま進化させることができるので一人で完結できるのはありがたかったですね。
是非これは今後の本編でも継続してほしい仕様ではありましたね。
また、今作でも「リージョンフォーム」のポケモンたちが存在しており、新しい姿のポケモンたちが出てきました。主的には一切情報がなかったのもありますが、「ヒスイヌメイル」と「ヒスイヌメルゴン」の実装は嬉しかったです。
そんな感じで、過去作よりポケモンを捕まえたり進化させたりすることが簡易的になったり新しい進化条件やフィールドのわくわく感などで集めるのが楽しくなっている作りになっております。
フォトモード
主個人的にフォトモードは楽しかったです。過去作にはなかった新要素ですね。
フィールドや村のなかで、Switch本体のスクリーンショット機能をつかってそのまま撮ることができますが、少しこじゃれた写真を撮りたいときにはかなりオススメです。
主はこのフォトモードで色々なポーズやレンズなどを使用して、お気に入りのポケモンと撮れるのがなによりも楽しかったです。

難点としては、バリエーションはそこまで多くないことと、ポケモンたちは動くのでシャッターチャンスを狙うのに時間がかかるのもあります。
今作はポケモンの歴史の中でも過去を描いているので、少しレトロな雰囲気を味わえるので記念として撮ってみてはいかがでしょうか。
実際にフォトモードを利用して撮った、主人公とヒスイヌメイルのツーショットです。
広くて懐かしい新しいヒスイ地方の冒険
今作は上記でも書いていますが、第4世代の「ダイヤモンド・パール」、リメイク作品の「ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール」の舞台である「シンオウ地方」の昔である「ヒスイ地方」が舞台となっております。

フィールド探索型ではありますが、ひとつひとつのフィールドが広くそして名前も「マサゴ平原」や「帳岬(トバリみさき)」などシンオウ地方の街の名前になっている場所もあったりしてちゃんとリンクしているなと思いました。
サン・ムーン以来の「ライドポケモン」が実装されており、この広々としたヒスイ地方のフィールド駆け抜けることができますし、ライドポケモンに関しては今作で初登場した新ポケモンたちが活躍しているのは嬉しいポイントですね。
また、フィールドだけではなくそれぞれの組織にいるキャラクターも「ダイパ」に限らず過去作に登場した作品のご先祖様だと思われるキャラクターもたくさんおり、シリーズの「繋がり」を感じました。
BGMも所々でダイパのBGMの別アレンジも流れておりここにも懐かしさを感じました。
物語もポケモンと人間の交流、それそれの組織の対立と和解が丁寧に描かれており、そして主人公がこのヒスイ地方に来た理由…etc、個人的にはすごくよかったです。
また、あくまで今作は「図鑑の完成」が目標なのでそこを乗り越えた先にこの作品のタイトルが回収される点については良かったと思う点でした。是非このタイトル回収についてはプレイしてご自身の目で確認してもらえたらと思います。
個人的に良くなかった点
個人的に良くなかった点は以下です。一部に関しては友人の話を聞いて思ったことも含んでいます。
- アクション初心者にはなれるのに時間がかかる
- バトルの難易度
- 難易度が高いサブクエストがある
それでは、1つづつ見ていこうと思います。
アクション初心者には慣れるのに時間がかかる
主はやや苦手な部類でそこそこは遊べるので一応初心者ではないのですが、がっつり初心者の姉や友人のSちゃん曰く
「操作が難してまだ慣れない(´;ω;`)」
と言っておりました。
実際ゲーム画面上に操作ガイドはあるものの、元々不慣れな人はやはり難しいようでポケモンを投げたいのにボールを投げっちゃったりなど臨機応変な対応には時間がかかっていました。
ある程度アクション要素は慣れてない人向けの配慮はされておりますが、アクションは失敗を繰り返してなんぼなところもあるので、慣れない時間を耐えられるかもお勧め度に影響はしてくるかなと思いました。
「時空のゆがみ」のなかでは、特に出てくるポケモンたちも珍しかったり強かったり気性が激しいポケモンが多く、やたらと主人公を狙って攻撃をしてくるので逃げ回るのに手一杯になったりもします。そこで攻撃してくるポケモンもいて主人公の体力が尽きたりなども多々ありました。
バトルの難易度

今作のバトルシステムは過去作より難易度が上がっていると感じました。
まず新要素の「力業/早業」ですが、適切なタイミングで使えるといいバトルができるのですが、使い方を間違えると一発で倒したり倒れたり、連続で行動されたり、連続行動の上で捕まえることもできるのでなど駆け引き要素になりました。
「特性」の概念もない(とあるポケモンを除く)ので本来「ふゆう」持ちのポケモンにじめんタイプの技が効いたりなど今までの常識が通じないのもあります。
バフ/デバフ(能力の一時上昇/下降)もこうげきととくこうは別で上昇していましたが今作は攻めの上昇はこうげきととくこう両方が上がる仕様になっており、場合によっては一撃で倒されたりもありました。
このような変更点は、いい意味で味を出している分難易度をあげてしまってとっつきにくい要素にもなっている印象でした。
もちろん、この新要素は図鑑を埋めるたり進化するのにも必要な要素ではありますので本当に使い方次第だなと思います。
あとは、場合によっては1対複数のバトルになることがあり連続で複数のポケモンから攻撃されてこちらのポケモンが一方的に倒されてしまうなど少しだけ理不尽なところもありやや調整
難易度の高いサブクエストがある
サブクエストの種類はアップデート後で約120ほどに増えましたが、そのなかでもいくつか難易度が高いものが存在しています。
細かい箇所までフィールドを探索しつつ回収したり、ヒントが本作の中ではなくリメイク作品の「BDSP」にあったり、条件が体長制限だったりとネタバレになるので詳しくは語らないのですが、本当にこの辺りは苦労しました。
これらすべてはサブクエストなので、本編の息抜きであるのですがその中でもわりと難しいので時間がかかると思っていただけると幸いです。
総評
総評としては、ポケモンの新たな挑戦をすごく楽しめた1作品になっていると感じました。
ちなみに主は本編クリアまでに約45時間、全ポケモンゲットとアップデートクリアまで約95時間かかりました。

主はアクションRPGは得意ではないほうなので、やや遅いほうかなと思います。
先日発表された本編の新作はオープンワールドとなっており、前作の「ソード/シールド」や今作のエッセンスがつまった新作になるのではないかなと今から期待しています。
主的には
- 対戦要素よりポケモンを集めるのが好きな方
- ポケモン好きでアクションRPGに挑戦してみたい方(初心者なら努力時間を含む)
は楽しめると思いました。
逆に
- アクションは苦手で過去挫折した方
- 対戦要素を期待していた方
はあまり楽しめないかなと思います。
主的お勧め度:8点/10点
本日の締めの挨拶
「PokémonLEGENDSアルセウス」の感想でした。
主としては初めてのゲームレビューで不慣れな点もありましたが、あくまで個人の感想ではありますので参考程度にして頂けると幸いです。
次回は「アイドルマスターSideM」の「Mフェス2022」のコラボ催事の感想とレポートを上げる予定でいますのでお楽しみにして頂ければと思います。
それでは、次回の更新をお楽しみに。
by織‐シキ‐
にほんブログ村
にほんブログ村
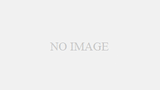

コメント